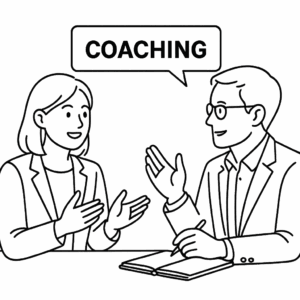― 行動変容を支える脳科学的アプローチ
はじめに:コーチングの「行動変容」をどう支えるか
コーチングの目的は、クライアントが今までの習慣的な行動を変え、望む目標へ近づくこと。
言い換えれば、「行動変容の支援」です。
しかし、なぜ人は変わるのが難しいのでしょうか。
どんなに意識しても、気づけば元の習慣に戻ってしまう…。
その理由を、私はここ数年「脳科学」の視点から探っています。
習慣は“脳の構造”と深く結びついている
参考にしたのは、ラッセル・A・ポルトラック著『習慣と脳の科学』(美鈴書房)。
この本の中で特に印象的だった一節があります。
「長期的な目標に沿って行動をコントロールする人間の能力は、脆弱な前頭前野に依存しており、
ストレスや集中を妨げる要因があると、簡単に中断され、元の習慣に戻ってしまう。」
つまり、人間は“理屈では分かっていても”前頭前野の働きが乱れると、
無意識に古い行動パターンへと戻ってしまうということ。
これは心理的な意思の強さではなく、脳の仕組みの問題でもあるのです。
心理学理論の限界と、科学的アプローチの必要性
心理学は行動変容を理解するための有効な学問です。
しかし、実際には数百人〜数千人の被験者をもとにした「統計的な仮説」にすぎません。
さらに興味深い指摘として、同書では次のように述べられています。
「心理学における行動変容理論は117もある」
「心理学者は他人の理論を歯ブラシのように扱う。
自尊心のある人間なら他人のものは使わない。」(W.ミシェル)
つまり、理論が多すぎて統一されていないのが現状です。
コーチングを実践する立場として、どの理論を根拠にすべきか悩む瞬間も多い。
そこで私が注目したのが「脳科学」です。
心理学的な“心の働き”だけでなく、
実際に脳の中で何が起きているのかを理解することで、
行動変容の仕組みをより現実的に説明できるようになると感じています。
「行動を変える」には脳のトレーニングが必要
人は本能的に「危険を回避すること」に意識が向きやすく、
遠い未来よりも“目の前の課題”を優先してしまう傾向があります。
これは、生存のためにDNAに刻まれた性質でもあります。
だからこそ、長期目標に沿った行動を続けるためには、意識的なトレーニングが必要なのです。
コーチングでは、
- クライアントにたくさん語ってもらう
- 自分の思考や行動を言語化して整理する
- 現実を客観的に見る「メタ認知」を育てる
といったアプローチを通じて、
前頭前野を活性化させ、“脳の再教育”を行っています。
コーチングを「科学」として進化させるために
私は、心理学的な理論を否定するつもりはありません。
むしろ、心理学と脳科学を統合していくことが、
これからのコーチングに求められる姿だと考えています。
- 科学的根拠に基づく行動変容の方法を取り入れる
- 最新の知見で自分のアプローチをアップデートし続ける
- クライアントの成長を“再現可能なプロセス”として支える
そのために、日々学び、試し、進化し続けたいと思います。
まとめ
「変わりたいのに、戻ってしまう」
これは意思の弱さではなく、脳の特性。
だからこそ、行動変容を支援するコーチには、
脳科学的な理解が欠かせません。
私のコーチングは、
心理学だけでなく脳科学を根拠にした行動変容支援を軸としています。
興味を持たれた方は、ぜひ一度体験セッションでお話ししましょう。
🔗 体験コーチングのご案内
体験コーチングセッション(少額)、単発セッション申し込み
まだ諦めていない。
でも、今のやり方では限界を感じている。
もし、あなたがそう感じているなら、それは “変わる準備ができた合図” です。