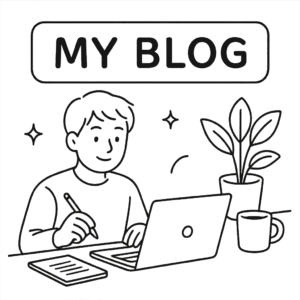日本のスポーツ指導は「教育」と言えるのか?
あなたはどう感じますか?
あなたのまわりのスポーツ指導は、本当に教育と言えるものでしょうか。
選手の人生を長期的に豊かにする学びになっているのか、それとも「次の試合の勝利」だけに執着してはいないでしょうか。
短期的な勝利に偏る現状
日本のスポーツ指導は、しばしば「教育の一環」として位置づけられています。
ところが現場を見てみると、多くの指導が「目の前の勝利」を追うことに偏ってはいないでしょうか。
教育とは本来、学生に長期的な利益をもたらすものであり、スポーツを通じて人間形成を促すこともその一部です。
人間形成とは、単に礼儀や規律を身につけさせることではなく、人生を豊かにする力を育むことに他なりません。
もし勝利だけに執着するなら、それは教育の本質から外れ、「幼児がおもちゃを欲しがるような短期的思考」に陥っているように見えます。
長期的利益を生む指導へ
一方で、海外のスポーツ指導や企業文化を見れば、「最終的に利益をもたらすこと」が徹底されています。
アメリカ企業は社員の能力を引き出すためにコーチングを活用し、最終的に収益やイノベーションにつなげています。
スポーツ現場でも、長期的育成(LTAD)を軸に「勝つ選手」よりも「成長し続ける選手」を育てる文化が根付いています。
ここで鍵となるのが、ICF定義のコーチングです。
- 選手を対等なパートナーとして扱う
- 問いかけを通じて自律性を育む
- 短期成果ではなく、長期的なキャリア形成を支える
このアプローチは、日本のスポーツ指導が抱える「近視眼的な勝利偏重」を補い、教育としてのスポーツを本来の姿=人生を豊かにする学びの場へと戻す力を持っています。
結びに
教育の本質を「長期的利益」とするなら、目の前の勝利にとらわれる指導はあまりにも視野が狭いと言わざるを得ません。
これからの指導者に求められるのは、短期的成果と長期的利益のバランスをとり、最終的に選手の人生を豊かにする指導です。
そのために、ICF的コーチングは極めて有効なアプローチであり、日本のスポーツ指導が成熟していくための大きな希望の道筋だと考えます。