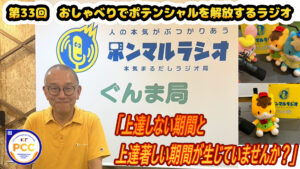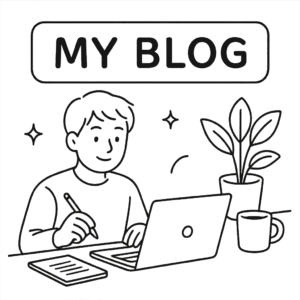教える×教えないでパフォーマンスアップ
スポーツコーチングは教えること?
公認スポーツ指導者の更新研修でスポーツコーチは何をしている人?と訊いています。すると、テクニックや戦術、ルールなどを教える人。と大多数の方が答えます。
それはそうだよね。確かに。
それが故に、選手の時に活躍していたひとをコーチにするチームは多いです。
ところが海外に目を向けると,コーチは「選手が成長することを促す人」みたいな意味になっています。
日本と海外のスポーツコーチの役割を比べてみる
日本では「技術を教える」「人間形成を担う」という意識が強い一方、海外では「選手の可能性を引き出す伴走者」「環境を整えるファシリテーター」としての役割が重視されています。
下の表では、日本と海外のコーチング文化の特徴を分かりやすく比較しました。
| 観点 | 日本の傾向 | 海外の傾向 |
|---|---|---|
| 役割の捉え方 |
|
|
| リーダーシップ様式 |
|
|
| コミュニケーション |
|
|
| レビュー文化 |
|
|
| 主体性・自律性 |
|
|
| チーム文化の設計 |
|
|
| スポーツサイエンス活用 |
|
|
| ステークホルダー連携 |
|
|
※ 一般的傾向の比較です。競技・レベル・地域・指導者個人の方針により差があります。
これはOpenAIで作成してもらいました。
僕はこれは言い得ている。的を得ていると思います。
主体性を育むために
海外は、教える。<教えない。という環境が整っていて、選手が自律的に練習を行うようになっています。
学習が未熟な場合、教えるという選択肢があります。それでも、選手が吸収したいと思う方が吸収率が高いことは事実です。そのような環境を提供していくことがこれらのスポーツ指導になっていくのだと思います。
日本において、海外のスポーツコーチのコーチングを学ぶ環境があまりにも少なすぎます。そして、海外のスポーツコーチングを体験できていないから、今までのスポーツコーチの中には懐疑的な面があります。
海外のスポーツコーチングはICF定義のコーチングに近いのです。特に対話部分ではほぼ一致していると思うのです。
あなたもICF定義のコーチングセッションを体験!
日本における指導者と選手対話で海外のスポーツコーチング型を身につけることで、「教える×教えない」というスポーツ指導者になれるのです。
これらかのアスリートを育成するために、まずはあなた自身がICF定義のコーチング対話を実感してみませんか?
体験コーチングセッション(少額)、単発セッション申し込み
まだ諦めていない。
でも、今のやり方では限界を感じている。
もし、あなたがそう感じているなら、それは “変わる準備ができた合図” です。