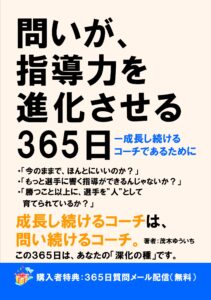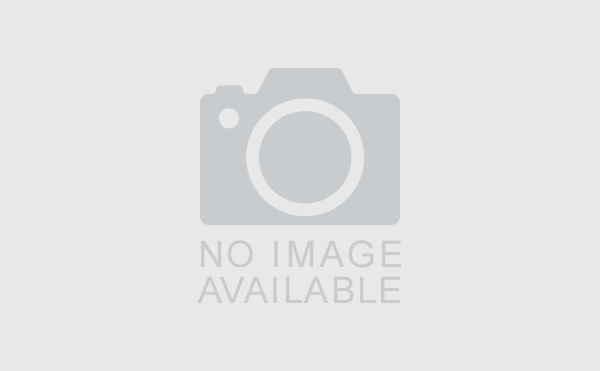このままでは、あなたは「パワハラ指導者」になってしまう?
こんな声がけしてませんか?
「なんでできないんだ」
「根性が足りない」
「ちゃんとしろ」
この言葉、どれかひとつでも、練習中に口にしたことはありませんか?
もし思い当たる節があるなら――
あなたはすでに、“パワハラ予備軍”の一員かもしれません。
「昔はこれが普通だった」という呪縛
多くの指導者は、自分が受けてきた指導を「正しい形」として信じています。
「俺たちの時代は、これで強くなった」
「厳しさが人を育てる」
確かに、その指導法で結果を出してきた人もいるでしょう。
しかし、それは“時代”が支えてくれた結果です。
今は違います。
社会も、選手も、脳科学も、教育理論も――
もう「根性論」では人は育たない時代になっています。
変わらない指導者の共通点:「危機が来るまで学ばない」
多くの指導者は、危機に追い込まれない限り、学ぼうとしません。
- 成績が落ちても、「選手のせい」
- チームの雰囲気が悪くても、「やる気の問題」
- 辞める選手が続いても、「今の子は弱い」
……すべて外に原因を求める。
これを心理学では「危機依存型学習」と言います。
痛みを感じないと、学びが始まらない。
事故やクレーム、SNS炎上、報道被害――
そうした“危機”に晒されて、ようやく学びの扉を叩く。
しかし、そのときにはもう遅いのです。
「パワハラ」は意図して起きない
多くの“パワハラ指導者”は、もともと選手の成長を願っている人です。
悪気はなかった。
ただ、「伝え方を知らなかった」だけ。
- 「ちゃんとしろ」→ 具体的に何を?
- 「頑張れ」→ どこをどう頑張る?
- 「やる気を見せろ」→ どんな行動を指す?
こうした曖昧な言葉が、誤解と恐怖を生みます。
指導者が意図しなくても、選手は萎縮し、
指導現場は“静かなパワハラ環境”に変わっていく。
海外では、コーチ同士が学び合う
欧米では「Community of Practice(学習共同体)」という環境・制度があります。
コーチ同士が対話を通じて、互いの現場を学び合う。
成功も失敗も共有し、支え合いながら成長していく。
日本ではどうでしょう?
学びは“上から与えられるもの”であり、
「他人の指導を批判するのは失礼」とされる。
結果として、孤立した指導者が、独自の正義を固めていく。
そして、その“正義”が、時にパワハラを生みます。
では、どうすれば変われるのか?
- 自分の言葉を記録する。
練習中の声かけを録音・記録して、後で聞き返してみましょう。
“自分がどう聞こえているか”を知ることが第一歩です。 - 対話の場に出る。
他のコーチのやり方を知り、意見を交わす。
「自分の方法しかない」という思い込みを壊す。 - 外部の専門家と関わる。
ICF認定コーチなど、対話的な指導を専門とする人と交流することで、
言葉の精度が変わります。
「指導」と「支配」は紙一重
指導とは、本来「指し、導くこと」です。
相手を動かすことではありません。
恐怖で支配することでもありません。
あなたの言葉が、選手を育てることもあれば、
選手の人生を壊すこともある。
その境界線を自覚することが、よりよい指導者の第一歩です。
あなたは、変われる
「このままでは、パワハラ指導者になる」――
これは脅しではありません。
あなたの成長のチャンスを示す“警告”です。
変わることは、恥ではありません。
学ぶことは、弱さではありません。
むしろ、“学び続ける指導者”こそが、次の世代を救うのです。
次の一歩へ
あなたが変わることで、選手も変わります。
まずは、自分の指導と言葉を見直すところから始めましょう。